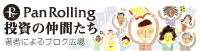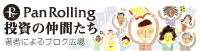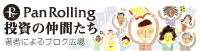
優利加の「生涯現役のトレード日記」
中東の地政学リスクの高まりを背景に日米株価は反落
02月20日
昨日の米国株式相場は反落した(DJIA -267.50 @49,395.16, NASDAQ -70.91 @22,682.73, S&P500 -19.42 @6,861.89)。ドル円為替レートは155円台前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が296に対して、下落銘柄数は1,262となった。騰落レシオは110.44%。東証プライムの売買代金は7兆1368億円。
TOPIX -44 @3,808
日経平均 -642円 @56,826円
米国では、イランとの核協議を巡る地政学リスクの高まりを警戒して株式相場は反落した。軍事力の行使をチラつかせてイランの譲歩を迫るため、トランプ米大統領は中東に既に原子力空母打撃団を派遣しており、最終的にイランに軍事攻撃をするかしないかを10日以内に決定すると述べた。もし軍事攻撃する場合、イスラエルとの合同作戦になると見られ、大規模な軍事行動となる。その場合、中東からの原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が一時的に封鎖される可能性も高い。それを反映して原油相場が上昇した。また、米連邦準備制度理事会(FRB)はこれ以上は利下げしないだけでなく、反対に利上げに転換する可能性すら浮上して来た。米資産運用会社ブルー・アウル・キャピタルが14億ドルのローン資産を売却し、一部のプライベート・クレジット・ファンドの解約を制限すると発表した。プライベート・クレジット・ファンドの流動性低下が懸念され、ブルー・アウル株は約6%(一時10%)下落し、同業のブラック・ストーンやアポロ・グローバルも5%超下落した。主要3株価指数は揃って反落した。
本日2月20日の東京市場では、地政学リスクの高まりを反映した米国株の反落の流れを受けて、日本株の多くも売り優勢となり、日経平均の下げ幅は一時700円を超えた。3連休を控えていることもあり利益確定売りが優勢となった。それでも第2次高市早苗政権の経済対策に対する期待が根強く、下値では押し目買いが入った。「国策銘柄」であるIHIや川崎重工は引き続き買われた。他に逆行高となった銘柄は、データセンター向け電線需要が拡大している住友電気工業や、AIサーバー向け銅箔の売り上げが好調な三井金属だが、これらの共通項は「AI(人工知能)関連銘柄」である。
日経平均の日足チャートを見ると、ギャップダウンして始まった後さらに下げて短陰線で終わった。昨日の上昇分以上に下げた。上向きの10日移動平均線の上に辛うじて留まり、株価サイクル③(着実な上昇局面)を維持したが、もし米国株はさらに下げると一旦このサイクルは終了しそうである。
今、株式相場が気にしていることは(1)中東の地政学リスクの高まり、(2)米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策転換の可能性、の2つである。そしてもう一つ付け加えるなら、(3)AI(人工知能)に対する投資が過剰でリスクに見合うリターンが得られるかどうかという不安である。
33業種中29業種が下げた。下落率トップ5は、証券(1位)、輸送用機器(2位)、空運(3位)、その他金融(4位)、繊維製品(5位)となった。
日米両政府合意の対米投融資案件が動き出したことで・・・
02月19日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +129.47 @49662.66, NASDAQ +175.25 @22,753.64, S&P500 +38.09 @6,881.31)。ドル円為替レートは155円台前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,115に対して、下落銘柄数は428となった。騰落レシオは120.81%。東証プライムの売買代金は7兆1048億円。
TOPIX +45 @3,852
日経平均 +324円 @57,468円
米国では、トランプ米大統領が湾岸戦争以来の大艦隊をイラン沖合にを集結させてイランを威嚇しており、イランを巡る地政学リスクが高まったことが株式相場の頭を抑えたが、エヌビディアやアマゾンドットコムなどをはじめとして大型テック株が買われた。2025年12月米耐久財受注額は前月比で予想されたほど下げなかったし、2026年1月米鉱工業生産指数も市場予想を上回った。つまり、米経済の底固さが感じられ、これからの企業収益向上への期待が高まった。主要3株価指数は揃って続伸した。
本日2月19日の東京市場では、対米投融資のガス火力発電事業の担う企業が明らかになり、電線各社に対する需要が高まると見て、電線大手の住友電気工業やフジクラなどが買われた。ガス火力発電の事業規模は333億ドル(約5兆2000億円)である。また、日米両政府が対米投融資の第2弾として次世代原子炉建設を検討しているとも報じられた。火力・原子力発電所向け部材を製造する日本製鋼所は昨日18日に既に2.46%上昇したが、本日19日も続伸して9.19%上げた。火力・原子力発電向け高温高圧バルブを手掛ける岡野バルブ製造はストップ高まで買われた。
AI(人工知能)投資などの需要と非中核事の売却が進み、資本効率改革を通して、業上場企業の2026年3月期の純利益は、前期比2%減だったものが、1%増へ変化し、5年連続で最高益を更新する見通しとなった。東証プライム上場の3月期決算の約1000社の業績予想を日本経済新聞社が集計した。5年連続最高益は比較可能は2008年の金融危機以降で初めてのこと。2025年4〜12月期に約250社が業績見通しを上方修正した。自己資本利益率(ROE)は今期予想を発表している約600社の集計から、「伊藤レポート」発表以来一つの目安となっている8%を超える企業は62%になる。
これからは米連邦準備制度理事会(FRB)が利下げを慎重に判断するとの見方が急浮上して来た。1月27〜28日に開いた米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録を公開した。これまでは、追加利下げを推進する意見と政策金利を当面据え置く意見の対立構造だった。しかし、今回は何人かの参加者は将来の利上げ転換の可能性についても言及し、「物価上昇率が目標を上回り続ける場合、政策金利の引き上げが適切になるかもしれない」と述べた。これは、これ以上米ドル金利が下がらない可能性が高まったことを意味し、それは即、外為市場に影響を与えた。ドル買いの増加により、円安ドル高が進んだ。
日経平均の日足チャートを見ると、ギャップアップして始まったが、戻り売りに押し戻されて上下にひげを引き「十字線」で終えた。寄付き後の売り買いの力が拮抗して終えたことを意味する。
注意すべきは、FRBの政策金利に対する姿勢が今までの「利下げ主流」から「場合によっては利上げもあり」に転換しそうな兆候が出てきたことを考えると、米国株はこれまでのような強い上昇基調を維持するのは難しくなりそうだ。もし、米国株式相場が調整モードに入れば、日本株も無傷ではいられなくなる。
33業種中28業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属(1位)、ゴム製品(2位)、鉱業(3位)、銀行(4位)、不動産(5位)となった。
4連続陰線による調整を経て、陽線で下げ止まった
02月19日
昨日の米国株式相場は小幅高となった(DJIA +32.26 @49,533.19, NASDAQ +31.71 @22,578.38, S&P500 +7.05 @6,843.22)。ドル円為替レートは153円台前半の前日比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,188に対して、下落銘柄数は352となった。騰落レシオは121.27%。東証プライムの売買代金は6兆4194億円。
TOPIX +46 @3,807
日経平均 +577円 @57,144円
米国では、前週末の1月米消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ったことで、米連邦準備制度理事会(FRB)の追加利下げ観測が高まった。これは株式相場全体を下支えしている。他方、人工知能(AI)開発新興のアンソロピックが、2月17日に新しいAIモデル「クロードソネット4.6」の提供を開始したと発表した。これはソフトウェア事業の売り上げにとっては逆風となると受け止められ、セールスフォースやマイクロソフトが売られてた。主要3株価指数は揃って小幅高となった。
本日2月18日の東京市場では、米国市場でハイテク株が小幅高となったことに加えて。本日発足する第2次高市早苗早苗内閣の財政出動や日米関係強化による需要が株式相場を押し上げた。東京エクトロンやTDKなどの主力銘柄をはじめとして、非鉄金属、保険、銀行株などが目立って買われた。日経平均の上げ幅は一時800円を超えた。
日米関税合意に基づく対米投融資の第1弾プロジェクトが決まった。工業用人工ダイヤモンドの製造プロジェクトも入っており、ノリタケや旭ダイヤなどの日本のダイヤモンド工具メーカーが関心を示しているため、両社とも株価が約4%上昇した。人工ダイヤモンド製造の他に、ガス発電施設、原油積出港の整備もこの一連のプロジェクトに入っており、事業規模は360億ドル(約5.5兆円)である。
この文脈でガス発電を手掛ける三菱重工が上昇した。三菱重工はエナジー部門が業績拡大を牽引しており、その主力がガスタービンの排熱を活用して蒸気タービンを回す「ガスタービン・コンバインド・サイクル(GTCC)」と呼ばれる高効率のガス火力発電プラントである。生成AI(人工知能)がさらに普及すると電力需要もさらに高まると予想されるため、発電効率の高いガスタービンへの更新が相次いでいる。三菱重工の大型ガスタービンの受注台数は2025年4〜12月期の累計では31台となり、既に2025年3月期の25台を上回っている。同業の川崎重工(3%高)やIHI(4%高)も上げた。さらに、火力・原子力発電所向け部材を製造する日本製鋼所も4%上昇した。放電精密加工研究所(三菱重工が大株主で同社に部品を提供している)はストップ高まで買われた。
逆行安となったのは続落したソフトバンクグループ(SBG)である。米アンソロピックが最新のAIモデル「クロードソネット4.6」の提供を始めたと報じられ、同社の最上位モデルに近い性能を4割安い料金で使えるようにするとのことである。ただでさえ米国のAIインフラに巨額投資をする「スターゲート計画」も投資に見合ったリターンが得られるかどうか不透明感が高まっていることに加えて、今回のニュースでアンソロピックの競合であるオープンAIに出資するソフトバンクグループはAI市場の競争激化により期待収益が悪化するとの懸念が高まっているためである。AIへの巨額投資に懸念を抱いているのがウォレン・バフェット率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイである。2025年10〜12月期にアマゾン・ドット・コムの保有株を前四半期比77%削減したことが2月17日に分かった。
2025年4〜12月期決算を発表した3月期企業の内、過去5年以上比較可能な約2,700社を対象に日本経済新聞が集計した結果、純利益が過去最高となった企業の数は822社、つまり30%となった。この比率は2006年4〜12月期(33%)以来19年ぶりの高水準である。足元の株価上昇はその反映である。但し、株価を動かす力は常に1〜2年先の予想収益であるため、事業環境の急変により業績見通しの下方修正が強く予想される場合、直近の過去の業績がどんなに良くても株価は必ず下がる。「株価P=予想EPS X 予想PER」が原理原則・鉄則である。ますます進化している生成AIの脅威により日米のソフトウェア関連銘柄が足元で軒並み下げている現実を見れば容易に理解できるだろう。
日経平均の日足チャートを見ると、陰線で4日続落した後、本日短陽線で反発した。これで調整は一応終わり、反発を試しに行きそうだ。株価は2月6日からずっと10日移動平均線の上に留まり続けており、株価サイクル③(着実な上昇局面)を継続している。
33業種中30業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属(1位)、保険(2位)、医薬品(3位)、その他金融(4位)、ガラス・土石(5位)となった。
「下放れ並び黒」に続き、本日は定石通りにさらに下げた
02月17日
昨日の米国株式市場は祝日のため休場だった。ドル円為替レートは152円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が677に対して、下落銘柄数は865となった。騰落レシオは119.64%。東証プライムの売買代金は6兆3092億円。
TOPIX -26 @3,762
日経平均 -240円 @56,566円
本日2月17日の東京市場では、衆議院選後に急上昇した過熱感がまだ意識されて、主力株は売り優勢となった。日経平均に対するウェイトが大きいソフトバンクグループが大幅下落した。米株式市場でソフトウェアなどのハイテク株が足元で下げており、同社が運用するファンドの運用成績が悪化するとの懸念が高まっているからである。日経平均の下げ幅は一時600円を超えたが、2月18日に発足する第2次高市早苗内閣の経済政策に対する期待は根強く、下値では買いが入り下げ幅を縮小した。外為市場での円高ドル安進行も株式相場の重しとなった。
日経平均の日足チャートを見ると、昨日の「下放れ並び黒」に続き、本日は定石通りにさらに下げて始まり下げ幅を拡大した。しかし、売りが一巡すると切り返し始めて下ひげを引いた短陰線で終えた。まだ上向きの10日移動平均線の上に位置しており、株価サイクル③(着実な上昇局面)は継続している。
33業種中17業種が下げた。下落率トップ5は、銀行(1位)、情報・通信(2位)、サービス(3位)、倉庫・運輸(4位)、機械(5位)となった。
下放れ並び黒
02月17日
先週金曜日の米国株式相場は高安まちまちとなった(DJIA +48.95 @49,500.93, NASDAQ -50.48 @22,546.67, S&P500 +3.41 @6,836.17)。ドル円為替レートは153円台前半での動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が805に対して、下落銘柄数は742となった。騰落レシオは125.18%。東証プライムの売買代金は7兆2376億円。
TOPIX -31 @3,787
日経平均 -136円 @56,806円
先週金曜日の米国では、1月米消費者物価指数(CPI)が予想を下回った(前月比+0.2%<予想+0.3%、前年比+2.4%<予想+2.5%)ため、米10年債利回りは低下して(4.104%から4.048%へ)株価を押し上げる力となった。他方、幅広い産業でAI(人工知能)が生産性を向上させるため、既存の仕事を奪い、業績悪化懸念が意識されて株価を押し下げる力となった。主要3株価指数は高安まちまちとなった。
本日2月16日の東京市場では、米ダウ工業株30種の上昇と2月18日に発足する第2次高市早苗内閣の経済政策への期待から買い優勢で始まった。しかし、2025年10〜12月期の国内総生産(GDP)速報値は、物価変動分を除く実質で前期比+0.1%、年率換算でわずか+0.2%と、市場予想を下回った。特に輸出が弱く、足元では円高ドル安も重なるためトヨタ自動車など自動車銘柄は売られた。米国の輸入関税の悪い影響が続いていることを暗示する。このようなことを背景に、買いが一巡すると次第に戻り待ちの売りに押し戻された。銀行株など内需関連銘柄の一角も売り優勢で下げた。さらに、外為市場で円相場が円高ドル安方向へ動いたことも株価の下押し要因となった。目立った動きとしては、ソフトバンクグループが後場になると一段高となり日経平均を支えた。また、銅などの資源価格の上昇を追い風に資源関連銘柄の回復が目立つ。三井金属は2026年3月期の業績見通しを、従来は減益予想だったものを、一転して最高益になるとの予想を発表したため、株価は大幅高となった。
日経平均の日足チャートを見ると、下放れた後、陰線が2日並ぶ「下放れ並び黒」となった。定石的な解釈は下方向の圧力が強く、まだ下がるというメッセージである。さて、今回は定石を跳ね返すかどうか。2月20日には高市早苗首相の施政方針演説がある。その内容次第では急反発もありうるが。
33業種中21業種が下げた。下落率トップ5は、ゴム製品(1位)、銀行(2位)、精密機器(3位)、卸売(4位)、輸送用機器(5位)となった。
AIがソフトウェア・サービスを侵食するとの警戒感が再び高まったため・・・
02月13日
昨日の米国株式相場は大きく下落した(DJIA -669.42 @49,451.98, NASDAQ -469.32 @22,597.15, S&P500 -108.71 @6,832.76)。ドル円為替レートは153円台前半での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が267に対して、下落銘柄数は1,305となった。騰落レシオは123.01%。東証プライムの売買代金は10兆7625億円。
TOPIX -63 @3,819
日経平均 -698円 @56,942円
米国では、AI(人工知能)が既存企業の業務に取って代わるとの懸念が引き続き意識されて、ソフトウェア株やIBMなどの大型ハイテク株が売られた。半導体価格の高騰により弱い決算見通しを示したシスコシステムズは2桁の急落となった。資産運用の分野でもAI利用に浸食されるとの見立てから、収益悪化懸念が強くなったPモルガン・チェースやゴールドマンサックスなどの金融株も売られた。さらに、銀先物相場が約10%急落した。主要3株価指数は揃って大きく下落した。
本日2月13日の東京市場では、もともと短期的な過熱感が強かったところへ、米国株の大幅安が重なり、日本株全般は野村総研、富士通、SHIFTをはじめとするソフトウェア株や大型ハイテク株を中心に幅広い銘柄が売り優勢の展開となった。ソフトバンクが大幅安になり1銘柄で日経平均を約340円押し下げて、日経平均の下げ幅は一時900円を超えた。ただ、米国の時間外取引で市場予想を上回る決算を発表した半導体製造装置のアプライドマテリアルズが10%以上上昇したこともあり、売りが一巡すると、同業のアドバンテストや東京エレクトロンなどの値がさ半導体が切り返し始めた。
日経平均の日足チャートを見ると、短期的な過熱感を跳ね返しながら高値圏で陽線による3日連騰(赤三兵)をした後、昨日は短陰線出現により一服感を暗示し、その翌日である本日、さらに陰線で下げた。ここまでは定石通りである。
33業種中24業種が下げた。下落率トップ5は、鉱業(1位)、鉄鋼(2位)、サービス(3位)、建設(4位)、情報・通信(5位)となった。
高値圏で3連続陽線で大きく上昇した(赤三兵)後に短陰線が出現すると・・・
02月13日
昨日の米国株式相場は小幅下落した(DJIA -66.74 @50,121.40, NASDAQ -36.01 @23.066.47, S&P500 -034 @6,941.47)。ドル円為替レートは153円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数は1,058に対して、下落銘柄数は503となった。騰落レシオは131.39%。東証プライムの売買代金は9兆9441億円。
TOPIX +27 @3,882
日経平均 -11円 @57,640円
米国では、1月米雇用統計で、非農業部門雇用者数(NFP)が予想以上に増加(13.0万人増>予想5.5万人増)し、失業率は予想では横ばいだったが実際には改善した(4.3%>予想4.4%)ため米経済が堅調であると受け止められた。その結果、追加利下げ期待は後退し、米10年債利回りは上昇した(4.145%から4.172%へ)。主要3株価指数は揃って小幅反落した。しかし、半導体関連銘柄は堅調で、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は2.28%上昇した。
本日2月12日の東京市場では、円高ドル安進行に加えて、短期的な過熱感を警戒した利益確定売りが増えたが、米国市場で半導体関連銘柄が買われたことを背景に、利益確定売り圧力をほぼ吸収した。しかし、円高ドル安進行を反映して自動車などの輸出関連銘柄は売りが優勢となった。2月10日、AI製品向け需要の増加に支えられ、JX金属は2026年3月期(今期)の連結営業利益を前期比33%増の1,500億円に上方修正した。これを好感して株価は一時18%上昇し、ストップ高まで買われた。同じくAI向けパッケージ基盤の需要が拡大しているイビデンは、10日、米指数算出大手MSCIが「グローバルスタンダード指数」に日本株ではイビデンを新規に採用すると発表したため、同社株は一時8%高まで買われた。
2月6日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高(期近・期先合計)は3週間ぶりに増加し、前週比5,530億円増加して、2兆9155億円となった。これは2018年1月12日(2兆9444億円)以来、約8年1か月ぶりの高水準である。株価が急速に上昇する過程では、流動性が高い先物が機関投資家にまず買われることが多く、現物よりも少し速く上がる。すると先物価格は理論値よりも高くなるため、割高な先物を売り、割安な現物で指数のポートフォリオを買う取引、つまり、裁定買い取引が増える。先物の期日(限月)には先物価格と現物価格は必ず同じ値になるので、裁定取引を行った時の差額が利益になるためだ。これが継続すると、裁定買い残が積み上がることなるが、どこかで(限月かその前に)必ず反対売買が起こり、利益確定売りが増加して相場全体の頭を抑えることになる。
日経平均の日足チャートを見ると、3日連続で陽線(赤三兵)が出て大きく上昇した後に陰線が出現して上値が重そうな罫線となった。こうなると経験則ではしばらく調整することが多い。過去半年くらいを遡ると、1月9日からの連続3陽線、10月29日からの連続3陽線、10月2日からの連続3陽線、8月6日からの連続6陽線の後に調整が起こった。ただ、あくまで調整の範囲内であり、大きなファンダメンタルズの変化がない限り、中長期の基調が変わるわけではない。
33業種中23業種が上げた。上昇率トップ5は、鉱業(1位)、非鉄金属(2位)、電気・ガス(3位)、卸売(4位)、水産・農林(5位)となった。
過熱感が高まっているが、「音楽が鳴っている間は・・・」
02月11日
昨日の米国株式相場は続伸した(DJIA +20.20 @50,135.87, NASDAQ +207.46 @23,237.68, S&P500 +32.52 @6,964.82)。ドル円為替レートは155円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は続伸する銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,313に対して、下落銘柄数は247となった。騰落レシオは135.39%。東証プライムの売買代金は9兆738億円。
TOPIX +72 @3,855
日経平均 +1,287円 @57,651円
米国では、ビットコインの下落が一服し、半導体株やソフトウェア株の買い戻しが起こっている。エヌビディアやオラクルが大きく上げた。主要3株価指数は揃って上昇した。
本日2月10日の東京市場では、米国市場でのハイテク株高に加えて、2月8日に投開票された衆院選挙で自民党が地滑り的大勝利を収めた(単独で2/3議席を確保)ことがもたらす期待が、昨日に続いて本日も継続した。日経平均は前場で上げ幅を1,600円近くまで拡大する場面があった。2月9日の午後に2026年3月期連結純利益見通しを180億円(前期比62%増)に上方修正した古河電工は2日連続でストップ高となり、2日間で48%強上昇した。AI市場の急拡大により米ハイパースケーラー(大規模クラウド事業者)からの受注で、光ファイバーの需要が膨張しているが供給が間に合わない状態が続いている。古河電工(予想PER約28倍)は競合のフジクラ(予想PER約42倍)や住友電工(予想PER約21倍)とともに投資家の注目と買いを集めてきた。
国内債券市場では、新発10年物国債の利回りは前日比0.0040%低い2.235%で終えた。中国当局が同国銀行に対して、米国債保有を抑制するように勧告していると報じられたことで、外為市場で円高ドル安が進行した。これにより円安ドル高の動きが一服したので、日銀が早期に利上げする必要性が低下したと市場が考ええ、長期金利は下げた。また、高市早苗首相が、2年間の時限措置である食料品の消費税減税は特例公債(赤字国債)に依存しないと改めて説明したため、財政懸念がやや後退したことも貢献した。
日経平均の日足を見ると、2日間で約3,400円も上昇した。日経平均の25日移動平均線乖離率が7.5%まで拡大し、RSI(14日ベース)も74.5まで上昇した。また、東証プライムの騰落レシオも135%まで上昇している。どの指標で見ても過熱感を示している。ただ、機関投資家は「音楽が鳴っている間は踊り続けなければならない」宿命を負っているので、オーバーシュートが頻繁に起こる。上昇基調はしばらく継続すると見るが、適宜調整が入るのも避けられず、それは「あるかないか」の可能性の問題ではなく、「いつか起こるか」という時間・タイミングの問題である。
33業種中29業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属(1位)、その他金融(2位)、不動産(3位)、情報・通信(4位)、鉱業(5位)となった。
米国株の大幅高と自民党の歴史的大勝利のダブル効果により大幅続伸!
02月10日
先週金曜日の米国株式相場は大幅高となった(DJIA +1,206.95 @50,155.67, NASDAQ +490.63 @23,031.21, S&P500 +133.90 @6,932.30)。ドル円為替レートは156円台前半での動きだった。本日の日本株全般は上げた。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,252に対して、下落銘柄数は293となった。騰落レシオは130.93%。東証プライムの売買代金は10兆4558億円。
TOPIX +85 @3,784
日経平均 +2,110円 @56,364円
先週金曜日の米国株式相場では、週の初めから大きく売られて下げていたエヌビディア、ブロードコム、オラクル、パランティア・テクノロジーズ等のAI関連銘柄に押し目買いが入った。人工知能(AI)が業務用ソフトを代替して駆逐するとの見方が急浮上したためにこの週は大きく下げていたソフトウェア銘柄の下げが一服し、半導体関連銘柄を中心に買いが広がった。ハイテク成長株から景気循環株への乗り換えの流れも継続した。ビットコイン価格も下げ止まりから反発し始めた。さらに、急落していた金銀価格も反発して相場センチメントの改善につながった。2月のミシガン大学・米消費者態度指数が57.3(>予想55.0)と予想を上回った一方、1年先予想インフレ率は3.5%(<前月4.0%)と低下した。つまり、過度の景気懸念が和らぐ一方、FRBの追加利下げを妨げるインフレ率が低下していると受け止められた。主要3株価指数は揃って大幅高となった。ダウ工業株30種の1日の上げ幅としては2025年4月9日以来の大きさとなった。
本日2月9日の東京市場では、米国株の大幅高と衆議院議員選挙での自民党の圧倒的大勝(戦後最多316/465議席)という大波に支えられて、幅広い銘柄が買われて日経平均は一時3,000を超える大幅高となった。高市早苗内閣は人工知能(AI)や半導体、防衛など17分野を戦略分野として掲げている。その関連分野であるアドバンテストは14%も急騰し、フジクラも急伸した。防衛銘柄である三菱重工やIHIも大きく買われた。2000年以降の今回の前までの9回の衆院選で、4回、自民党が単独で60%以上の議席を取った。その4回すべてで日経平均は総選挙の前営業日と60日後・120日後で比較すると上昇した。安定与党は政策を実施し易くなるし、政治の安定を重視する海外投資家の買いが増えるからだ。
自民党が圧勝したが、財政負担増加を懸念する債券売り(=長期金利上昇)は増えなかった。10年物新規国債利回りは一時前週末比0.055%高い2.280%となる場面があったが、与野党が選挙公約した消費税減税の財源をどうするかのという懸念を背景に1月20日に記録した今年の最高水準である2.380%からは遠い。ただ、税源問題が解決したわけはない。さらに、来月に予定されている日米首脳会談で米トランプ大統領はさらなる防衛費増強を求めてくるはずであり、その恒久財源はどうするのかという財源問題が蒸し返されて長期金利の上昇圧力は高まるはずである。
日経平均の日足チャートを見ると、ギャップアップして始まるとさらに上値を追い、上ひげを引いた長大陽線で終えた。本日の東証プライムの売買代金は10兆円を超えるほど大商いだった。余裕で株価サイクル③(着実な上昇局面)を継続したが、1日でこれだけ急上昇すると、明日は利食い売りにより調整する可能性が高いとみる。
本日の寄り付き後10分ほど観測していて、三菱UFJは高く始まった後、陰線を描き始めていたので成り行きで持ち株は全て一旦利食い手仕舞いしました。「二刀流燕返し」の建玉法なので、手仕舞い売りした直後に、再上昇し始めたときに備えて「売りの返し」、つまり「買い」の注文を逆指値で入れておきました。これで上げても良し、下げても良しの構え「偃月殺法」の構えです。
33業種中30業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属(1位)、不動産(2位)、機械(3位)、建設(4位)、電気機器(5位)となった。
ページの先頭へ
ブログトップへ
PC版へ