著 者 ピーター・C・オッペンハイマー
監修者 長岡半太郎
訳 者 藤原玄
トレーダーズショップから送料無料でお届け
本書は、ゴールドマンサックスのチーフ・グローバル・エクイティ・ストラテジストであり、「株式のゴットファザー」であるピーター・オッペンハイマーによる、前著『ザ・ロング・グッド・バイ(The Long Good Buy)』の続編である。本書では、成長率やインフレや金利といったマクロの要因の構造的な変化がどのように地政学や社会の変化と結びつき、市場の長期的なトレンド(スーパーサイクル)に影響を及ぼすかを学ぶことになる。
オッペンハイマーは、長期的なトレンドと、そのなかで進展する短期的な市場のサイクルのさまざまな要因に関する見識を伝えてくれている。彼は次の長期的なトレンドである「ポストモダンサイクル」に焦点を当てており、その考えらえる特徴とともに投資家が注目すべきことについても説明している。彼は来るポストモダンサイクルと、それを形作るだろう技術的なイノベーションと脱炭素化の相互作用について分かりやすく伝えている。
本書では、第2次世界大戦後の好景気、1970年代のインフレ、その後の長期にわたるディスインフレ、グローバリゼーションの影響や金融危機後のサイクルの政策によって与えた影響といった過去のスーパーサイクルの歴史とその要因が詳述されている。ポストモダンサイクルはこれら過去のサイクルの要素を反映するだろうが、地政学的な状況の変化や気候変動とともに、急速な技術の発展によって再編されている世界で独特の特徴を持ち、まったく異なる問題と機会をもたらす可能性が高い。
本書は市場のサイクルに関心のある者たちにとっては必読本である。近年の経済史、そして金融市場の将来がどのようになるかについて新しく、深淵な見識をもたらしてくれる!
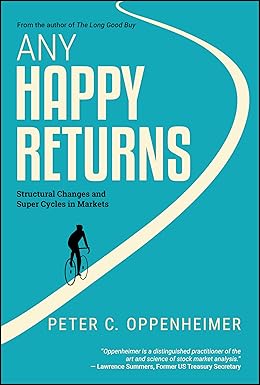
ゴールドマン・サックスのチーフ・グローバル・株式ストラテジストであり、グローバル・インベストメント・リサーチ部門の欧州マクロリサーチ部門の責任者。およそ40年にわたってマクロの調査アナリストとして従事し、ゴールドマン・サックスの前はHSBCのチーフ・インベストメント・ストラテジストを務めていた。1985年にキャリアをスタートさせたグリーンウェルズをはじめ、ジェームズ・カペルやハンブローズ・バンクでさまざまな調査に携わってきた。ナショナル・インスティテュート・オブ・エコノミック・アンド・ソーシャル・リサーチとアンナ・フロイト・ナショナル・センター・フォア・チルドレン・アンド・ファミリーズの理事も務めている。趣味はサイクリングと絵画。
原題: Any Happy Returns: Structural Changes and Super Cycles in Markets by Peter C. Oppenheimer
「景気変動、そして金融のサイクルは重要である。ピーター・オッペンハイマーはそれを十分に理解している。だが、社会、経済、政治、テクノロジーの要素が組み合わさることで、過去が信頼に足る指針とはならなくなるときがある。オッペンハイマーは、われわれの世界の構造的な変化を反映するポストモダンサイクルというアイデアを紹介している。本書はわれわれが現在の圧政から解放され、大局的に考え、報酬を手にする機会を与えてくれる」――アレクサンダー・ウィリアム・ヤンガー卿(前MI6[英秘密情報部]長官)
「過去と未来を見事に紡ぎ、歴史、文化、政治を経済分析に組み込むことで、ピーター・オッペンハイマーはこの啓蒙的で、洞察力に富む独創的な1冊を記した」――ノリーナ・ヘルツ教授(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、インスティテュート・フォア・グローバル・プロスペリティー)
「『ザ・ロング・グッド・バイ』という素晴らしい前著に続き、ピーター・オッペンハイマーはこのとても刺激的な新著で、金融市場のサイクルの分析を深化させている。彼は金融市場のサイクルを大きなトレンドと結びつけるだけでなく、地政学、テクノロジー、経済、社会の変革とも結びつけている。筆者はポストモダンサイクルの出現、そしてそれが広範囲に与えるだろう影響を見定め、伝えている」――ジョセ・マニュエル・バローゾ元欧州委員会委員長・ポルトガル首相)
「ピーター・オッペンハイマーが思慮深く、洞察力に富んだ1冊を著した。彼はサイクルが持つ役割を伝えてくれているが、それはわれわれがサイクルのどこにいるのかだけでなく、今後どのようになりそうかを理解するうえで役に立つ」――コフィ・アジェポンボーテンCBE(ケンブリッジ大学センター・フォア・ファイナンシャル・ヒストリー研究員)
「数多くのトレンドが展開する金融市場のスーパーサイクル(長期的なトレンド)の包括的な分析を通じて、オッペンハイマーは数多くの新しく、有益な知見をもたらしてくれている。雄弁に綴られた本書は、データに基づく証拠やチャートやトレンドを用いて根底にあるメッセージを簡潔に伝えてくれる。金融市場の投資家、実務家、研究者、規制当局にとっては必読の1冊である」――ナラヤン・ナイク(ロンドン・ビジネス・スクール教授)
第1章 サイクルと長期トレンドの概論(立ち読みページ)
繰り返されるサイクル
社会的・政治的サイクル
景気循環
金融市場におけるスーパーサイクル
心理学と金融市場のスーパーサイクル
第1部 構造的トレンドと市場のスーパーサイクル
第2章 株式のサイクルとその原動力
株式のサイクルの4つの局面
4つの局面の原動力
サイクルと弱気相場
弱気相場から強気相場への移行を見定める
第3章 スーパーサイクルとその原動力
経済活動のスーパーサイクル
近代――1820年代以降の成長
インフレのスーパーサイクル
金利のスーパーサイクル
スーパーサイクルと政府債務
格差のスーパーサイクル
金融市場のスーパーサイクル
株式のスーパーサイクル
第2部 戦後のスーパーサイクル分析
第4章 1949〜1968年 第2次世界大戦後の好景気
国際的な取り決めとリスクプレミアムの低下
力強い経済成長
技術的なイノベーション
低く、安定した実質金利
国際貿易の活況
ベビーブーム
消費と信用の拡大
夢中になる消費主義
第5章 1968〜1982年 インフレと低リターン 投資家にとっては失われた10年
第6章 1982〜2000年 モダンサイクル
1.グレートモデレーション
2.ディスインフレと資本コストの低下
3.サプライサイドの改革(規制緩和と民営化を含む)
4.ソ連の崩壊(地政学的リスクの低下)
5.グローバリゼーションと国際協力
6.中国とインドの影響
7.バブルと金融のイノベーション
第7章 2000〜2009年 バブルとトラブル
ハイテクバブルの崩壊
2007〜2009年のリーマンショック
レバレッジと金融のイノベーション
長期的な成長期待の低下
株式のリスクプレミアムの増大
債券と株式の逆相関
第8章 2009〜2020年 リーマンショック後のサイクルとゼロ金利
1.低成長だが、株式のリターンは高い
2.フリーマネーの終焉
3.低ボラティリティ
4.株式のバリュエーションの拡大
5.ハイテク株やグロース株がバリュー株をアウトパフォーム
6.アメリカが世界各国をアウトパフォーム
第9章 パンデミックと「ファット・アンド・フラット」リターン
パンデミックの大混乱
パンデミックとインフレ
ディスインフレからリフレへ
現実に立ち返る――実際の資本コストが上昇に向かう
黄金律が再浮上する
主導するセクター、そしてバリュー株への旋回
第3部 ポストモダンサイクル
第10章 ポストモダンサイクル
構造変化とチャンス
モダンサイクルとの違い
1.資本コストの上昇
2.成長トレンドの鈍化
3.グローバリゼーションからリージョナリゼーションへの変化
4.人件費とコモディティ価格の上昇
5.政府支出と債務の増大
6.資本支出とインフラ支出の増大
7.人口動態の変化
8.地政学的緊張の高まりと多極化した世界
第11章 ポストモダンサイクルとテクノロジー
技術革新の特徴
熱狂、投機、そしてバブル
優性効果
二次的技術の登場
ハイテクは最大のセクターであり続けられるか
現在支配的な地位にあるハイテク企業はリーダーであり続けられるか
インターネットの世界の低い生産性
「あったらよいな」から「なくては困る」に
生産性とAIの影響
AIとテクノロジーのPEARLsフレームワーク
第12章 ポストモダンサイクル――「オールドエコノミー」のチャンス
「オールドエコノミー」のチャンス
国防費
インフラ支出
グリーン支出
政府の政策と支出
コモディティへの支出
どうすれば投資市場は資本投資ブームの役に立てるか
雇用の未来
ノスタルジーの力を忘れてはならない
自転車に乗って
第13章 まとめと結論
サイクル
スーパーサイクル
ポストモダンサイクル
参考文献
推薦図書と文献
本書はゴールドマン・サックスのチーフ・グローバル・株式ストラテジストであるピーター・C・オッペンハイマーによる“Any Happy Returns : Structural Changes and Super Cycles in Markets”の邦訳で、マクロ分析のなかでも、国単位でのGDP(国内総生産)やインフレ率や失業率や金利といった経済動向の分析を、過去の歴史を振り返りながら行い、その構造変化やスーパーサイクルを理解しようとする解説書である。
私はこの本を、投資家として大変興味深く読んだ。一般に投資家にとって必要な分析は、経済環境のマクロ分析、投資対象のファンダメンタルズ分析、さらに市場参加者の行動や心理の分析の3つである。そして、多くの人は各銘柄の良し悪しの分析やタイミングを計るための時系列のテクニカル分析に興味があるようだ。
しかし、投資や投機を専業にして生活している人は別として、ほとんどの個人投資家にとって重要なのはむしろマクロ分析である。なぜなら、投資のリターンの大半は、個別銘柄の選択やタイミングの巧拙ではなく、市場全体の動き(ベータ)で決まるからである。ゆえに日本の確定拠出年金(iDeCoなど)や少額投資非課税制度(NISA)のように家計の安定的な資産形成を目的とした投資においても、多くの投資家にとって重要な課題はアセットクラスの選択と配分(アセットアロケーション)にある。
ところで、アセットアロケーションによるポートフォリオ運用の最も簡便な方法は、いくつかの各アセットの配分を固定し、定期的(3カ月ごとや1年ごと)に粛々とリバランスしていくというやり方である。実際、そうした方法はほとんど手間がかからず迷いもない優れた投資戦略である。いわゆる「老後資金2000万円問題」の解決をはじめとして、将来の経済的な不安をなくし安心・安全を得るだけならそれで十分なのだ。
だが、もしあなたがさらに少しだけ手を加えて、自身のポートフォリオ運用をより良いものにしたいと思うならば、まず最初に試みるべきは、個別銘柄の選定やトレードタイミングを計ることではなく、マクロ分析によって現在および近傍の未来の経済環境を理解・予想し、各アセットの配分を機動的に少しだけ変化させることだろう。そのためには、何も機関投資家が行っているような、ビルディングブロック法やインプライド法による将来の期待リターンの推計を伴う精緻な分析や未来予測はまったく必要がない。本書で解説されているような金利の変化やインフレ率といった事実を確認しながら後追いで各アセットのイクスポージャー調整をゆっくり行うだけでも、固定式の配分によるポートフォリオ運用を有意に凌駕することができことだろう。
刊行にあたって以下の方々に感謝の意を表したい。藤原玄氏は正確な翻訳を行っていただいた。そして阿部達郎氏には丁寧な編集・校正を行っていただいた。また、本書が発行される機会を得たのは、パンローリング社の後藤康徳社長のおかげである。
2024年12月
長岡半太郎
「私は自転車に乗りながらそれを考えた」――アルバート・アインシュタイン
前著『ザ・ロング・グッド・バイ(The Long Good Buy)』は、景気循環と金融市場のサイクル、そしてそれに影響を与える要素を取り上げた。本書はそれを補うことを目的としている。過去と将来における経済・金融市場の長期的な構造変化と、サイクルが展開するさまざまな長期的トレンドに目を向ける。本書は学生や市場参加者、そして経済や金融市場の歴史や長期的パターンやトレンドの原動力となる要素に関心のある人々に向けたものだ。
金融市場には、短期的なサイクルと長期的なスーパーサイクルや長期的なトレンドのパターンが存在するが、その長期的なトレンドのなかで短期的なサイクルが見られる。短期のサイクルは景気循環と大いに関係する。1850年以降、全米経済研究所によると、アメリカ経済では景気後退が35回、主要な株価指数が20%以上下落する弱気相場が29回あった。第2次世界大戦終結以降で見ると、アメリカ経済の景気後退は13回、株式の弱気相場は12回である。
株式市場は景気循環に先行する傾向がある。第2次世界大戦以降、株式市場は平均すると景気後退の7カ月ほど前に高値を付け、経済が回復を始める7カ月ほど前に底を打ってきた。
景気循環や経済活動や金利といった経済的要素の変動だけでなく、その他さまざまな要素が市場に大きな影響を及ぼし、長期的なトレンドを左右する。その要素は地政学や技術的変化や制度変更から、政策の変更や社会における流行やトレンドの変化まで多岐にわたる。これら要素の構造変化が長期にわたり継続する長期的なトレンドやスーパーサイクルを生み出し、その間に景気循環や市場のサイクルが展開する。
例えば、低インフレが長期にわたり続けば、その間に数回の景気循環が起こることもある。同様に、強力な経済成長や経済の停滞が長きにわたり続くなかでも、短期的な景気後退に一時的ながら影響を受けることもある。このような長期的なトレンドには特定の市場状況や市場機会が付随することが多いが、それこそが本書で深く掘り下げようとするものだ。
第2次世界大戦以降、株式市場のスーパーサイクルは6回あった。これらスーパーサイクルの半分は長期にわたる強気相場、つまりリターンが極めて高く、バリュエーションが拡大する期間だった。残りの半分は「ファット・アンド・フラット」と説明できるかもしれない。つまり、値幅はそれなりにあるが、長期で見たリターンはあまりない期間である。
導入部の第1章では、社会的見解、政治的意見、経済や金融市場のサイクルをめぐる考え方の歴史、そして心理や人間の行動がそれらサイクルに与える影響に注目する。
その後、本書は以下の3部に分かれている。
第1部 構造的なトレンドと市場のスーパーサイクル サイクルとスーパーサイクルの歴史に目を向ける。
第2部 戦後のスーパーサイクル分析 第2次世界大戦以降のスーパーサイクルとその原動力となった条件を議論する。
第3部 ポストモダンサイクル 次のサイクルはどのように展開するか、その主たる特徴はどのようなものか、そしてそれがAI(人工知能)と脱炭素化という2つの要素からどのように影響を受け、規定されるかに目を向ける。前者はバーチャルな世界を規定し、後者は現実世界を多分に形づくることになる。
第2章では主に金融市場のサイクルと、それが、①絶望、②期待、③成長、④楽観の4つパターンを繰り返す傾向にあること、そしてその要因について説明する。
第3章では、長期にわたる主要な経済変数のスーパーサイクルを説明する。つまり、GDP(国内総生産)、インフレ、金利、債務、格差、金融市場などだ。
第4章では、1949〜1968年のスーパーサイクルの原動力について議論する。国際的な取り決め、背景にある強力な経済成長、技術革新、低い実質金利、世界貿易や消費や信用の拡大、そして人口動態に目を向ける。
第5章では、インフレと低いリターンに見舞われた1968〜1982年の期間に目を向け、高金利や低成長の影響、社会不安やスト頻発、世界貿易の崩壊、大きな政府債務と企業の利益率低下を取り上げる。
第6章では、私がモダンサイクルと呼ぶものを説明する。これは「大いなる安定(グレートモデレーション)」、ディスインフレ、資本コストの低下、そしてサプライサイドの改革の影響を特徴とする時期である。ソ連崩壊が地政学的リスクに与えた影響、グローバリゼーションの出現と国際協力の高まり、そして中国とインドの急成長の影響について議論する。
第7章では2000〜2009年を取り上げ、ハイテクバブルの崩壊から2008年のリーマンショックまで、新たな千年紀の最初の10年を特徴づけたバブルとトラブルに目を向ける。
第8章では、2009〜2020年のリーマンショック後のサイクルに大きな影響を及ぼしたユニークな状況とゼロ金利政策が市場リターンに及ぼした影響を見ていく。
第9章では、パンデミックがもたらした影響、具体的には政策に与えた影響と、経済的利益や市場リターンに関するデフレストーリーからリフレストーリーへの移行について議論する。
第3部 ポストモダンサイクル
第10章では、私がポストモダンサイクルと呼ぶものが出現する様子を説明する。そして、資本コストの上昇、成長トレンドの鈍化、グローバリゼーションからリージョナリゼーションへの転換、人件費と原材料費の上昇、政府債務の増大、インフラ支出の増大、高齢化、そして地政学的緊張の高まりが示唆することについて説明する。
第11章では、ポストモダンサイクルにおいてテクノロジーやAIが市場リターンをどのように形づくるかについて議論する。
第12章では、旧来の業界と、ポストモダンサイクルにおける脱炭素化やインフラ支出の増大から生まれるチャンスに焦点を当てる。
最後に、第13章で本書のまとめと結論を示す。
「過去をより遠くまで振り返ることができれば、未来もそれだけ遠くまで見渡せるだろう」――ウィンストン・チャーチル
『ザ・ロング・グッド・バイ(The Long Good Buy : Analysing Cycles in Markets)』では、金融市場のサイクルは時がたつにつれて繰り返し発生する傾向にあることに注目した。その市場のサイクルのほとんどは景気循環に左右される。もしくは、少なくとも景気循環に応じて推移する。サイクルは重要だが、投資家にとっては自分たちがサイクルのどこに位置するか、そして次に何が起こるかを予想することが最も重要となる。
つまり、金融のサイクルは景気循環を予測する一助になると言うこともできる。BIS(国際決済銀行)の金融局長であるクラウディオ・ボリオが述べているように、「金融サイクルのないマクロ経済学は王子のいないハムレットのようなものだ」。少なくともここ30年の環境では、第2次世界大戦以前の時期の環境と同じように、金融のサイクルを理解しなければ、景気変動やそれに伴う政策課題を理解することは不可能である。
金融のサイクルは経済や市場の変わらない特徴だが、より長期のトレンドや「スーパーサイクル」のなかで出現することが多い。この長期的なサイクルを主導する要素がリターンの強力なパターンを生み出し、景気循環の短期的な影響を目立たなくする。短期的なサイクルも重要だが、長期的なより大きなトレンドを理解することで投資家は長期に見たリターンを大幅に高めることができる。
例えば、低インフレ期が長く続けば、その間に景気循環は数回起こる。同様に、力強い経済成長や停滞期が長く続くこともある。その間も、短期的な景気後退に一時的な影響を受ける。このような長期的なトレンドには、特定の市場状況やチャンスが付随することが多い。ほとんどの投資家が時間と労力をかけて、サイクルの次なる展開や変曲点を理解しようとする。しかし、より長期の構造的な展開や変曲点のほうが重要であることが多いが、かなり安易に見過ごされてしまう。
『ザ・ロング・グッド・バイ』は新型コロナウイルスのパンデミックの間、イギリスで最初のロックダウンが始まるときに出版した。新型コロナが出現するまでは、大多数の人々が世界的な成長は力強いものになると考えていた。当時、深刻な脅威としてサプライチェーンやインフレの再現に注目している者はほとんどいなかった。地政学的な緊張がヨーロッパでの戦争の引き金になるという考えは現実離れしたものと思われていただろう。そのような個々の出来事を予想するのは不可能だった。だが、社会的・政治的展開や政策策定を重ね合わせてみれば、自分たちが重要な変曲点の初期の段階にあることが分かる。つまり、金融市場のリターンを左右する要素の多くが変わっているのだ。
導入部である本章が終わると、本書の主要部分は3つの部に分かれている。第1部では、サイクルと構造的なトレンドとの違いについて議論する。第2部では、第2次世界大戦後のスーパーサイクルの歴史とそれを特徴づける原動力を示す。第3部では、スーパーサイクルの出現とその潜在的な特徴について議論する。この新時代をポストモダンサイクルと呼んでいるが、それは第2次世界大戦後の期間の伝統的なサイクルの特徴のいくつかを示しているように思えるからだ。つまり、ボラティリティはより高く、リターンは低いが、1980年以降の期間に優勢となったボラティリティが低く、バリュエーションが拡大するモダンサイクルのいくつかの要素も見られる。
金融市場におけるサイクルの興味深い特徴の1つが、時がたつにつれて繰り返すように見えることである。経済的・政治的環境や政策環境が大きく異なるにもかかわらず、だ。最近の論文で、筆者のアンドリュー・フィラルド、マルコ・ロンバルディ、マレク・ラチェコは、過去120年間に、アメリカはインフレ率が低い金本位制の期間と、インフレ率が高く、変動が大きい1970年代を経験したと記している。同様に、この長い期間を通じて、物価を安定させるために中央銀行が取れる施策は移り変わり、財政政策や規制政策はかなり変化してきている。
サイクルは、われわれが理解する物理科学や自然界の至るところ出現する。それは天文学、地質学、気象学のサイクルから生物学や睡眠のサイクルまで多岐にわたる。ある様相が繰り返される傾向にあるというコンセプトは自然界だけでなく、人間の本質や社会でもはっきりと見て取れる。そのため、経済や金融市場においても明白である。社会的な優先事項や政治や国際関係や経済状況が複雑であること、そして相互に関連し合っているということは、これらのサイクルがそれぞれの時代に存在する、もしくは長期にわたり存在することを意味する。そして、そのサイクルは構造的なトレンドに応じたものであり、金融市場に根本的に異なる結果をもたらすということだ。
政治から社会的態度や流行や経済に至るまで人為的なシステムにおけるサイクルやトレンドは、長きにわたり認識されている(経済の発展や繁栄は長期的なサイクルまたは波のように展開するという考えは、19世紀のマルクス主義文学にも見られた。それらの書物では、経済におけるサイクルの主因として利益の変動に注目していた。以下を参照のこと。
古代のギリシャ人たちは政治的なサイクルに関心を持っていた。プラトンは『国家』でキクロス(またはサイクル)について語っているが、第8巻と第9巻は政府のさまざまな体制とそれぞれの移行に関するものだ。アリストテレスも『政治学』の第5巻で政府のサイクルと、その変化を引き起こすために取るステップについて記している。ポリュビオス(紀元前200〜118年)は、アナサイクロシスと呼ばれる国家のサイクルに関する理論を生み出したが、これは民主制、貴族制、君主制のライフサイクルとそれらが取る体制(衆愚制、寡頭制、独裁制)に関するものだ。このコンセプトはキケロやマキャベリの書物でも言及されている。
ローマ人は長期的な世代間のサイクルの重要性を理解しており、それをサエクレムという言葉で説明した。これは、一般に人間の寿命と定義される期間、または地球上の人類が完全に入れ替わる期間と考えられていた。例えば、戦争などの重大な出来事が発生した時点から、その出来事を直接経験したすべての人々が死亡するまでの期間と考えられた。中国人は易姓革命というコンセプトを生み出した。これは、歴史は強力な指導者が築き上げた帝国や王朝が次々に交代することで紡がれるというものである。強力な指導者の跡を襲った指導者たちは同程度の実効性を維持することができず、やがて王朝は衰退してしまうことになる。
金融市場のサイクルに影響を及ぼす要素はたくさんあるが、金利や成長率といったマクロの要素が重要となる。さらに、財務収益の長期的なトレンドは社会的・政治的サイクルに影響されるが、これは景気循環や金融市場のリターンにまで波及する大きな構造的変化を示すことがある。
社会や経済・政治体制が持つ多面的な影響や、それらの要素が互いに影響し合う様子に対する関心は時間の経過とともに進化している。啓蒙時代には、学者たちは概して「自然の秩序」と認識されていたものに注目し、文化的進化や社会発展の段階を説明するカテゴリーを生み出した。19世紀になると、文化的進化や社会の進化に対する認識はチャールズ・ダーウィンが『種の起源』(1859年)で展開した生物学的進化論に大いに影響を受けるようになった。社会的進化に関する理論が生まれたが、そこでは社会は有機体のようなものと考えられていた。この生物学的類推は、社会発展を理解する方法として人類学者や社会学者たちの間で人気となった。
社会学の分野における社会循環理論が、発展は恒常的なものだとする一方的な世界観に異議を唱えたことで、社会の発展はシクリカルな現象だという認識が注目された。シクリカルだとする考え方では、社会の発展をパターンがサイクルのように繰り返される傾向だととらえる。文化的進化は多重線形だとする理論も人類学の分野で展開された。これらの理論では、人類の文化や社会は、ちょうど政治的なサイクルや経済と同じように、そのときどきの環境に適応することで独自に進化すると仮定していた。フランツ・ボアズ、アルフレッド・クローバー、ルース・ベネディクト、マーガレット・ミードなどの人類学者は、文化に関する一般化に背を向け、さまざまな社会における文化的なプロセスを理解することに研究の焦点を当てた。この多重線形の次元で見ると、社会の発展は状況に応じたものであり、時間の経過とともに変化するものとなる。そのため、経済や金融市場と同じように、まるで同じような状況が展開しているかのように繰り返される。例えば、経済が低迷している時期には、長い目で見れば、環境はまったく異なっても社会不安や政治的な変革が付随することが多い。
20世紀に入ると、歴史家たちのサイクルに対する関心は高まった。オズワルド・シュペングラーは『西洋の没落』(1918〜1922年)で、生物学になぞらえて、個々の文明はライフサイクルを経験し、1000年ほどの長い期間を通じて、誕生から衰退または崩壊へと推移するとした。イギリスの歴史家で、経済学者であり、社会改革主義者でもあったアーノルド・J・トインビーも同様の結論に至り、1934年に12巻からなる『歴史の研究』の第1巻を出版し、循環理論を取り入れた。
政治学における長期サイクル理論の権威であるジョージ・モデルスキーは『世界システムの動態 世界政治の長期サイクル』(晃洋書房)で経済のサイクルや戦争のサイクルと世界の指導国の政治的側面との関係を説明した(政治学の分野にも似たようなコンセプトはある。アメリカ政治に関する研究でシュレシンジャーはリベラルと保守のサイクルの移り変わりを説明し、サイクルの原動力は「自己生成」し、やがて繰り返されるとした。
一方で、ハンチントンの研究では政治プロセスと政策へのアプローチの変化を引き起こす定期的に発露される「信条的な情熱」を見いだした。政治的な成功は経済的サイクルや社会的サイクルと密接に関連するようになっている。一定の環境下では概してある種の政党が政権を握るが、その環境が変化すれば政権も交代する。どの政党が政権を握るかは好況期または景気後退と関連しているのかもしれない。その政党の成功は広範な経済的変化や社会的変化を反映していることが多いのだ。
彼の研究は、1500年代以降、コンドラチェフの波で説明される経済的なサイクルとおおよそ連動した政治における長期的サイクルが5回発生していることを示している。このような非常に長期にわたる政治的サイクルは、覇権国の支配が及ぶ期間におおよそ基づいている。最初が16世紀のポルトガルで、その次が17世紀のオランダ、そしてイギリス(18世紀と19世紀)が続き、第2次世界大戦後にアメリカがその任を引き継いだ。
このように期間が長くなれば、その影響は経済活動ひいては金融市場にも及ぶ。これらの研究のほとんどはヨーロッパ基準もしくは「西洋基準」と言うべきもので、世界の他地域における発展期のほとんどを無視していた。例えば、紀元前2世紀から紀元15世紀まで経済成長を拡大し、文化的・宗教的な交流を後押しした6400キロの交易路である「シルクロード」を通じた交易は初期のサイクル分析では見落とされることが多く、それは7世紀のアラブのイスラム教徒の影響力や13世紀のモンゴル人たちの影響力も同様である。
国際舞台における権力闘争もサイクル、または長期的なトレンドの原因となるが、これは地政学や外交政策に対するアプローチの変化にも影響を受ける。
アーサー・M・シュレシンジャー(父子)はサイクル理論のなかで、アメリカの歴史に照らすと、アメリカはリベラルな態度が広がり民主主義が進展することで、社会が問題とその解決に目を向ける時期と、保守派が大勢を占め、個人の権利を重視する時期とが交互に出現し、それぞれの段階が次なる段階の原因になっていると主張した。彼らは、リベラルな局面では積極行動主義が疲れ果て、一方で保守的な局面では問題が解決しない期間が長く続いたあとにリベラルな風潮が高まると主張した。
クリングベルグも外交政策の領域におけるサイクルを、アメリカの影響力が拡大する「外向き」の時期と、政策が孤立主義的になる「内向き」の時期とが交互に訪れると説明した。彼は1952年の論文で、平均すると21年間の「内向き」の時期が4回あり、同じく27年間の「外向き」の時期が3回あると述べた。
社会的態度は経済状況に影響を及ぼし、またそれを反映するが、社会における文化的な表現も同様である。オスカー・ワイルドが「芸術が人生を模倣する以上に、人生は芸術を模倣する」と述べたことは有名だが、芸術的な運動に反映される社会的態度は、政治的展開や経済的展開を反映するとともに、その要因となることが多い。
例えば、1991年にハロルド・ズロウは1955〜1989年までにアメリカで人気となった上位40曲の歌詞を調査し、「反芻思考」と「悲観的説明スタイル」の兆候を探そうとした。彼は同じ期間のタイム誌の巻頭記事を調査し、同様の兆候を探したが、ポピュラー音楽に悲観的な反芻思考が増えると、1〜2年遅れて世界的な出来事に対するメディアの見方に変化が訪れることを発見した。彼はまた、ポピュラー音楽と世論調査に見られる消費者の楽観論、さらには消費者の支出パターンや経済成長(GNP)の間には統計的に妥当な関係があることを示した。ポピュラー音楽やニュース雑誌の悲観的な反芻思考は消費者の楽観論や支出の低下を通した景気後退の予兆となる傾向にある。
景気循環とそれが金融市場や株価に及ぼす影響に対する関心が高まったのは主に19世紀だった。キッチンサイクルは40カ月ごとに発生し、コモディティや在庫状況がその要因となる。資本投資を予想するために生み出されたジャグラーサイクルは7〜11年周期で、収入を予想するクズネッツサイクルは15〜25年の周期だ。サイクルに関する画期的な理論は1920年代にニコライ・コンドラチェフが生み出した。彼の研究は1790〜1920年までのアメリカ、イギリス、フランス、ドイツの景気動向に注目した。彼は、工業生産、コモディティ価格、金利を反映して50〜60年続く長期の成長サイクルを見いだし、これらはテクノロジーのサイクルが原動力になっていると主張した。
サイクルやトレンドに対する関心は大恐慌を受けて高まった。ケインズが『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936年)を出版したすぐあとに、ヨーゼフ・シュンペーターは『景気循環論 資本主義過程の理論的・歴史的・統計的分析』(有斐閣。1939年)で自らの理論を展開した。ケインズは政府の政策に注目したが、シュンペーターは企業や起業家の影響に着目した。彼は、およそ50年周期のコンドラチェフサイクルは、キッチンサイクル(3年ほど)やジャグラーサイクル(9年ほど)など、互いに重なり合う短期のサイクルから構成されると主張した。彼は、超長期のコンドラチェフサイクルは創造的破壊の結果だと考えた。これは、新しい技術が投資と経済成長を生み出し、一方で古い技術が廃れていくプロセスである。このような技術的なイノベーションが成長と繁栄期を呼び起こし、やがてその技術が経済のさまざまなセクターで広範に用いられるようになるにつれ、経済は低迷期に入る。
シュンペーターは長期のコンドラチェフサイクルを3つ見いだした。1つ目は1780年代から1842年までで、イギリスの第1次産業革命が関係した。2つ目は1842〜1897年で、これは鉄道というイノベーションに後押しされ、蒸気船や鉄道などの新しい技術を用いる工業国が鉄や石炭や織物などの経済機会から利益を獲得した結果だった。3つ目は電動化が推進力となった1898〜1930年代までで、電力や化学や自動車産業の発展や商業化が関係するが、彼は論文を記した時点ではサイクルは完了していないと考えていた。
サイクルを局面やトレンドに分割するこの方法論は、経済や金融市場ではより短期的な変動があるかもしれないが、その一方で大きなイノベーション、さらには社会的態度や政治や地政学に後押しされるより長期のトレンドも存在することを示している。