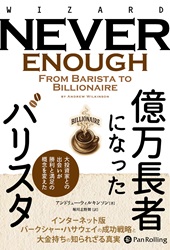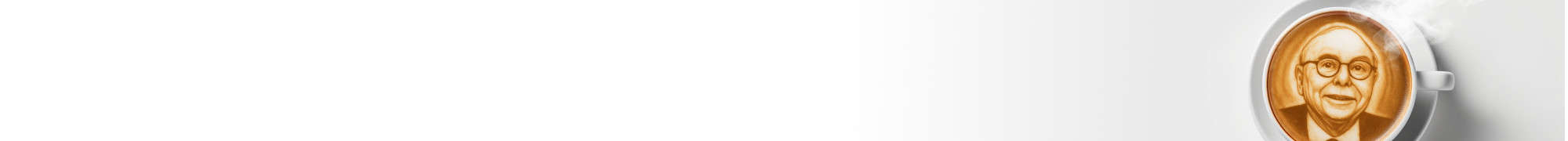

マンガー・オタクの僕が…
僕はクリスと一緒にTinyという会社を設立したとき、誰か一人だけ会いたい人を選ぶとしたら、それはチャーリー・マンガーだと話した。
マンガーとバフェットのブロンズの胸像まで特注して、オフィスのマントルピースの上に飾った。 オフィスを訪ねてくる人のなかには彼らを知らない人もいて、「あれは、君たちのおじいさん?」と訊かれることもあった。だが、多くの人は僕たちのヒーローに同じく心酔していて、すぐに気づき、自分たちにも同じものを注文してくれないかと頼んできた(どんなことにもビジネスのヒントを見いだす僕は、マンガーとバフェットの胸像を欲しがる人が大勢いることに気づき、これをサイドビジネスにしたところ、いまでも年間数万ドルを売り上げている)。
僕はマンガーとバフェットが買収した企業をどんな順番でも言える。
収益順、産業順、アルファベット順。アクメ・ブリック・カンパニー、ベンジャミンムーア、BNSF鉄道、デイリークイーン、デュラセル、フルーツオブザルーム、ガイコ……まだまだ続けてもいいけど、言いたいことはわかっただろう。『ジェパディ!』(アメリカの長寿クイズ番組。カテゴリーと金額ごとに問題が出題される)にマンガーとバフェットの持株会社に特化したバージョンがあれば、僕はケン・ジェニングス(『ジェパディ!』の連勝記録保持者)と競うことになっただろう。

バークシャー・ハサウェイ社の株価
「バークシャー・ハサウェイはこの会社の5.6パーセントを所有しています」
「アップルとはどんな会社?!」
「バークシャー・ハサウェイはこの会社の26パーセントを所有―」
「クラフト・ハインツとはどんな会社?!」
僕はこの大物たちに関する本を読み尽くしていて、つぎの買収に熱狂している中毒者みたいに、投資に対する彼らの英知を静脈注射していた(「大金は売買で得られず、待つことで得られる」)。
演劇ファンがミュージカル『ハミルトン』のお気に入りの場面を抑揚から何までそっくりそのまま暗唱できるように、僕も彼らの金言を高らかに歌うことができる(「まずまずの会社を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい会社をまずまずの価格で買うほうがはるかによい」)。
野球ファンがワールドシリーズの最終イニングを振り返るように、彼らの投資に対するリターンについて順を追って詳しく説明することもできた(バークシャー・ハサウェイの株価は1964年から2014年のあいだに180万パーセントという衝撃的な上昇率を見せている)。
だけど僕は、この会社の歴史を暗唱するだけの傍観者にはなりたくなかった。このゲームに参加したかった。いつの日か自分の会社の歴史を誰かに暗唱されるような人間になりたかった。
覚えているかぎりずっと、僕はひとかどの人物になりたいと思っていた。満ち足りた人間に。ジョブズに。ディズニーに。バフェットに。マンガーに。
これらの巨頭たちには遠く及ばなくても、普通の基準に照らせば、僕は成功していた。一から築き上げた僕たちの会社は30以上の子会社を所有し、1000人以上の従業員を抱え、何億ドルもの収益を上げている。僕たちの小さな帝国は、見たところばらばらの大小さまざまな業種から成る。20年近く仕事をしてきたなかで興味を持った事業で、それぞれが異なるニーズを満たしている。
そんな僕たちをマンガーに紹介してくれた共通の友人がいて、彼はマンガーが所有するテクノロジー企業のことで僕たちの力を必要とするかもしれないと伝えてきた。僕たちは巡ってきたチャンスに飛びつき、すぐさま会いに行く計画を立てた。人生のすべてはこの瞬間に繋がっていて、僕は好機を逃したくなかった。
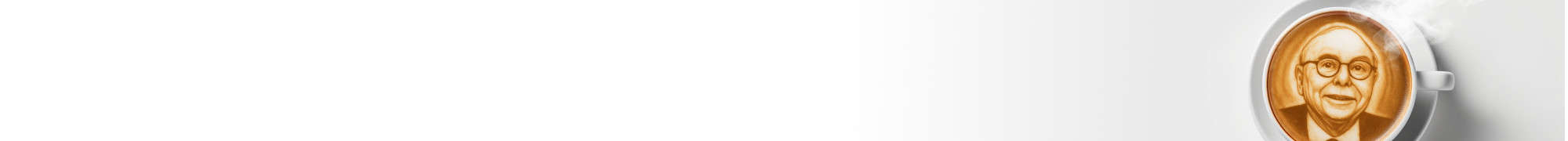

マンガー邸に招待され…
僕たちが床から天井まで古い書物がびっしり詰まった書斎に入ったとき、マンガーはレイジーボーイの椅子に座っていた。足を組み、傍らのテーブルには大量の本が山積みになっていて、二つの巨大なハロゲンライトがマンガーを美術館の彫刻みたいに照らしている。あとで知ったのだが、彼は数年前に白内障の手術が失敗したため片目の視力を失っていて、読書をするのにその明かりが必要だったのだ。
マンガーと向かい合って座っているのはアンドリュー・マークス、このディナーをセッティングした共通の友人だ。彼がマンガーに僕たちを紹介してくれた。
「チャーリー」マークスは礼儀正しく話を中断させた。
「こちらは私の友人のアンドリューとクリスです。二人はテクノロジー企業に焦点を合わせた、小さなバークシャー・ハサウェイみたいな会社をカナダに所有しているんですよ」
「やあ」僕たちをじっと見上げて、マンガーは言った。その顔は僕のオフィスのマントルピースに飾った胸像にあまりにもそっくりで、ドキッとしたほどだった。完璧なまでに丸い顔、薄くて細い白髪、太いワイヤーフレームの眼鏡。
「お会いできてとても嬉しいです、チャーリー」僕は興奮しながら言った。「あなたの大ファンなんです」
同じぐらい舞い上がっているクリスは、たったいま僕が言ったのと同じようなことを口にした。「大ファンです。お会いできてとても嬉しいです、チャーリー」(まるで、二人で一つの長い回文をつくっているみたいだった)
マンガーは97歳だったが、依然として頭は冴えわたっていることがすぐにわかった。
書斎で少しおしゃべりしたあと、ダイニングルームに通された。ピンクと緑色の花模様のタペストリーみたいな壁紙の部屋だ。席に座りながら、クリスも僕も適切な服装をしてきたことがわかり、ホッとした。マンガーはグレーのスーツのパンツに緑色のチェック柄シャツを着て、独自のスタイルとしてクッションのきいたデクスターのものとおぼしき靴を履いていた。デクスターは、1993年にバークシャー・ハサウェイが4億3300万ドルで買収した会社だ。
ディナーのあいだはマンガーが座の中心となったが、彼は僕が想像していたとおりの人だった。聡明。愉快。鋭い。
どこかのライターチームが考案していてもおかしくなさそうな至言に満ちていたが、それらはマンガーが自分の頭のなかから引っぱりだした言葉に間違いなかった。
「不景気の時期にビジネスをするのは、他人がプレーしているバドミントンのシャトルになるようなものだ」
ステーキをひと口食べながら言った。
「ある問題がどれだけ難しいかを理解した時点で、問題の半分は解決している」
フォークからサヤエンドウをぶら下げながら話した。ミックスグリーンサラダを食べながら、僕とクリスにこんな金言も授けた。
「すごい金持ちになるには、一度だけ正しくあればいい」
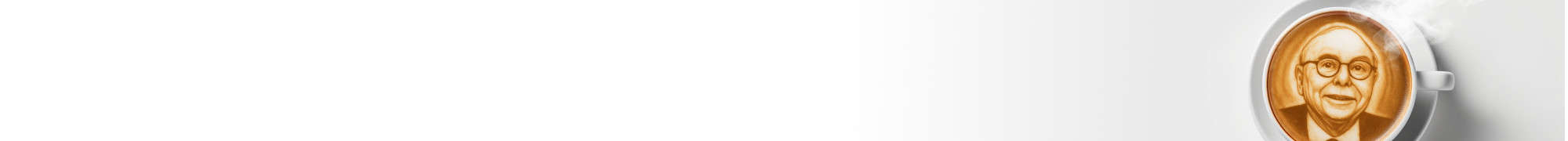

マンガーからぶっ飛びの提案を…
何年にもわたってバークシャー・ハサウェイに関する読み物に目を通してきたことから、ほとんどが知っている内容だったとはいえ、僕はすっかり興味をそそられていたが、そのあとマンガーが言ったことを聞いて、椅子から転げ落ちそうになった。

「じつは、私は君たちが興味を持ちそうな問題を一つ抱えていてね。マンガー家の財産の大部分はバークシャー・ハサウェイにあるが、1970年代に私と友人は法律関係の出版社を買収したんだ。当時の新聞社の大半と同じく、この会社は莫大な金を生んだが、2000年代初めからは下り坂になっている。その会社は存続していて、デイリー・ジャーナルという公開会社で、私が会長を務めている。昔ながらの出版業の衰退に伴って、われわれは法律関係のソフトウェア会社を買収した。こちらがこの事業の将来を担うことになるだろう。それに、金融危機の際に出版業のほうからも思いがけない利益を得て、いくらか株を買ったが、その後かなり価格が上昇している。しかし、一つ大きな問題がある」
ここでマンガーは一拍置いた。まるで僕たちが舞台上の役者で、脚本を読み上げていて、つぎは僕たちの台詞だというように。
「どんな問題が?」クリスと僕は前のめりになって同時に尋ねた。
「私がもう老いぼれだってことだ! 私は97歳で、CEOは83歳だぞ!」
僕らはどっと笑った。
すると、思いもよらないことが起きた。まず、マンガーは黙り込んだ―頭を働かせ、計算し、なんらかの代数方程式を解こうとしていたが、やがて僕らを見て言った。
「いいかね、君たちが株式を公開する方法はもう一つある」
「といいますと?」
「デイリー・ジャーナルを引き継いでくれる人間が必要だ。われわれが互いの会社を合併させて、君たち二人が実権を握ればいい。そちらは素晴らしいテクノロジー企業ばかり所有しているし、こちらには何億ドルもの投資すべき金と、君たちの専門知識を利用できるソフトウェア会社が一つある」
その瞬間、僕の頭のなかで誰かが巨大な“一時停止”ボタンを押したみたいだった。たったいま、チャーリー・マンガーは「われわれ」とか「互いの会社を」とか「合併」とか言ったのか? 僕はマンガーがソフトウェア事業のことで相談したがっていると知って、ここまで飛んできた。マンガーは何かパソコンのことで困っていて、インターネットの達人である甥っ子に助けを求めるようなものかと思っていた。会社の合併を提案してくるなんて、そんな大それたことは夢にも思わなかった。
僕は愕然とした。だけど、これが現実だ。
僕は慌てて適切な返事を考えた。「とても興味深いお話です」
震える手でデザート用のナプキンのしわを伸ばし、冷静で落ち着いた態度を必死に装いながら、マンガーに伝えた。本当はテーブルに飛び乗って、有頂天の悪態を叫びたくてたまらなかったのだけど。クリスも明らかに僕と同じくショック状態にあり、まるでたったいま顔にパンチを食らわされて、どう反応していいのかわからないというように、一時的に固まってしまっていた。
僕らがマントルピースの上の二つのブロンズ像になったみたいに、マンガーは僕とクリスを交互に見比べた。
「で?」マンガーの問いかけで、僕たちは現実に引きもどされた。
「どう、その、どういう体制の構築をお考えですか?」クリスが質問した。
こういう取引を成功させるにはどうすればいいか、マンガーは続けて要点を説明した。たとえば、クリスと僕が新会社の株式の過半数を保有し、マンガーとほかのデイリー・ジャーナルの株主が合併会社の残りを持つ。クリスと僕はその会社の対外的な顔になる。マンガーは取締役会に残り、それを通じて僕たちを指導する。日々の仕事はすべて僕たちが運営し、実際に株式を公開するという頭痛の種を抱えずに公開会社としての恩恵を享受することができる。じっくり考えてみてくれ、とマンガーは話を締めくくった。
マンガー邸をあとにしながら、僕たちは天にも昇る心地だった。ビジネス界のヒーローの一人と食事をしただけじゃなく、97年分の予言者の知恵の泉からひと口の水を分け与えてもらったばかりか、マンガーはカナダのビクトリアからたまたまやってきた二人組に、自分が尽力して築き上げた会社を引き継がせることを検討していたのだ。僕たちにバトンを渡すことを。
マンガー邸のドライブウェイで、クリスと僕は映画『トップガン』一作目のマーベリックとグースみたいに、飛び上がってハイタッチした。
「ヤバいな」車に乗り込みながら、僕はクリスに言った。
「あのチャーリー・マンガーと一緒に仕事できることになるなんて」
とにかく、これからそうなるんだと僕たちは思っていた。
――『億万長者になったバリスタ』第1章「いくらあればいい?」より
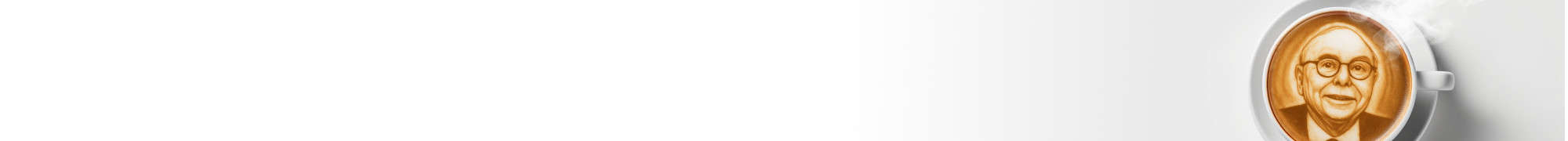

続きは本書でどうぞ
億万長者になったバリスタ
大投資家との出会いが勝利と満足の概念を変えた
2025年7月発売/四六判 並製400頁著 者 アンドリュー・ウィルキンソン
訳 者 堀川志野舞
ホーム > 発行書籍 > 『億万長者になったバリスタ』立ち読みページ