著 者 ベンジャミン・グレアム、ジェイソン・ツバイク
監修者 長岡半太郎
訳 者 井田京子
トレーダーズショップから送料無料でお届け

投資本なかで最高傑作とだれもが認めるベンジャミン・グレアムの『賢明なる投資家』を、ウォール・ストリート・ジャーナルの傑出した金融ジャーナリストであるジェイソン・ツバイクが各章ごとに現代の市場に合わせて解説を加えたのが本書である。
本書を読めば、グレアムが主張し続けてきた「バリュー投資」の奥義である「安全性分析(security analysis)」という普遍的原則を投資にいかに適用し、実践するかが手に取るように分かる。
なぜ、今、バリュー投資なのか? それは、グレアムの教えを忠実に守ったウォーレン・バフェットをはじめとする投資家たちの長期にわたる実績を見れば、だれも、そして、どんな反論も許されないことは明らかである。『賢明なる投資家』が80年近く、投資家を魅了し続けてきたことを、グレアムを師と仰ぐ者たちがパフォーマンスレコードで証明しているのだ。
また、ツバイクの解説を合わせて読むことによって、『賢明なる投資家』が一般投資家向けに書かれたことがよく分かり、初心者でも『賢明なる投資家』の理解度が一気に進み、読者の投資人生を激変させることになるだろう。
本書を読めば、成功への道筋はすぐそこに見えている! しかし、グレアムが何度も強調している「投資家にとって最大の敵は自分自身である」という箴言とも、もう1つの奥義とも言うべきものは、本書にも、地上にあるどんな本にも解決策は書かれていない。成功をするためには、読者自身が独自に自分で見つけるしかない。今、成功という名のボールはあなたのコートにある!
ベンジャミン・グレアム(Benjamin Graham、1894〜1976年)
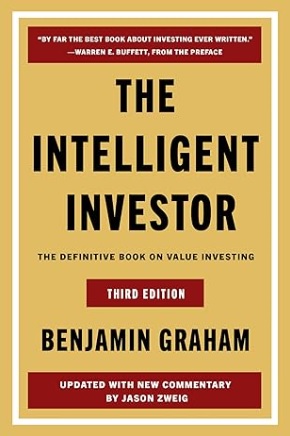 財務分析とバリュー投資の父と呼ばれ、世界中の成功したビジネスパーソンたちに何世代にもわたってインスピレーションを与えてきた。『証券分析』『賢明なる投資家』『賢明なる投資家【財務諸表編】』(パンローリング)などの著作がある。
財務分析とバリュー投資の父と呼ばれ、世界中の成功したビジネスパーソンたちに何世代にもわたってインスピレーションを与えてきた。『証券分析』『賢明なる投資家』『賢明なる投資家【財務諸表編】』(パンローリング)などの著作がある。
ジェイソン・ツバイク(Jason Zweig)
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の投資コラムニスト。投資について、さまざまな面から旺盛に執筆活動をしている。風刺を効かせたウォール街の用語集『金融版 悪魔の辞典』(パンローリング)、神経科学の視点から投資について書いた『あなたのお金と投資脳の秘密』(日本経済新聞出版社)などの著作がある。
「ジェイソン・ツバイクほど、ベンジャミン・グレアムの良き理解者はいないだろう。ツバイクは、最先端の学術研究、初心者にも分かる秀逸な解説、そしてウイットを駆使して、偉大なる師のアドバイスを21世紀に見事に復活させた。グレアムがこの『新賢明なる投資家【第3版】』のページをめくりながら、うなずき、そして苦笑いする姿を容易に想像することができる」――ウィリアム・バーンスタイン(『投資の4原則』[パンローリング]の著者)
「ウォーレン・バフェットを育てた人物によって書かれた不朽の名作を、人気の金融コラムニストであるジェイソン・ツバイクによる解説を加えた本書は、グレアムの普遍的原則がいかに今日的であるかを示している。本書は、すべての賢明なる投資家の本棚の最も見やすく、手に取りやすい位置に置くのをおススメする」――バートン・マルキール(『ウォール街のランダム・ウォーカー』の著者)
「ジェイソン・ツバイクは、ベンジャミン・グレアムの偉大な著書を、注と章ごとの解説でより深化させ、現代的な事例を『賢明なる投資家』の本に沿った鋭い洞察を加えることによって、真剣な投資家すべてにとって重要な利益をもたらした。熟練の投資家も初心者の投資家も、そしてその中間の投資家もみんな、この素晴らしい本を謳歌し、学ぶ時間を作ることで、楽しみながら利益を得ることができるだろう」――チャールズ・エリス(『敗者のゲーム』の著者)
第11章 一般投資家のための安全性分析
債券の分析/株の分析/資本化率に影響を与える要因/成長株の資本化率/業界の分析/二段階の評価プロセス
注
第11章 解説
第12章 EPSについて考慮すべきこと
平均利益の使い方/過去の成長率の計算
注
第12章 解説
第13章 上場企業四社の比較
四社に関する全般的な見解
注
第13章 解説
第14章 防衛的な投資家の株の選択
私たちの基準を一九七〇年末のダウ平均に適用する/公益企業という「解決策」/金融株への投資/鉄道株/防衛的な投資家の選択
注
第14章 解説
第15章 積極的な投資家の銘柄選択
グレアム・ニューマン方式の概要/二流の企業/株式ガイドの情報を精査する/株を一つの基準で選択する/正味流動資産価値を下回る割安銘柄/スペシャルシチュエーションまたは「ワークアウト」
注
第15章 解説
第16章 転換証券とワラント
転換証券が株に与える影響/普通株から優先株への切り替え/ストックオプションワラント/補足
注
第16章 解説
第17章 極めて教訓的な四つの事例
ペン・セントラル鉄道/リング・テムコ・ボート/NVFによるシャロン・スチール買収(コレクションとして)/AAAエンタープライズ
注
第17章 解説
第18章 八組の企業比較
一組目 リアル・エステート・インベストメント・トラスト(店舗、オフィス、工場ほか)とリアルティ・エクイティーズ・コープ・オブ・ニューヨーク(不動産投資、総合建設)
二組目 エア・プロダクツ・アンド・ケミカル(産業用、医療用ガスなど)とエア・リダクション・カンパニー(産業用ガスと機器、化学品)
三組目 アメリカン・ホーム・プロダクト(医薬品、化粧品、家庭用品、菓子)とアメリカン・ホスピタル・サプライ(病院用品、医療機器の販売・製造)
四組目 H&Rブロック(所得税申告サービス)とブルーベル(作業着、制服等の製造)
五組目 インターナショナル・フレーバーズ&フレグランス(他社向けの香料ほか)とインターナショナル・ハーベスター(トラック製造、農業機械、建設機械)
六組目 マグローエジソン(公益事業と設備、家庭用品)とマグローヒル(書籍、映画、教育システム、雑誌と新聞の出版、情報サービス)
七組目 ナショナル・ゼネラル(大規模コングロマリット)とナショナル・プレスト・インダストリー(多様な電気製品、軍需品)
八組目 ホワイティング(資材運搬機器)とウィルコックス&ギブス(小規模コングロマリット)
全般的な見解
注
第18章 解説
第19章 株主と経営陣――配当方針
株主と配当方針/株式配当と株式分割
注
第19章 解説
第20章 「安全域」――投資家の中心的な概念
分散投資の理論/投資と投機を区別する/投資対象の概念を広げる/まとめ
注
第20章 解説
あとがき
注
あとがき 解説
付録
一.グレアム・ドッド村のスーパー投資家たち
ウォーレン・バフェット
二.株の新たな投機性
ベンジャミン・グレアム
三.投資対象としてのハイテク企業
謝辞 ジェイソン・ツバイク
監修者あとがき
本書は、ベンジャミン・グレアムによる『The Intelligent Investor Third Edition : The Definitive Book on Value Investing』の日本語訳(下巻)である。本版には、グレアム自身が時代の推移に応じて加筆修正を施した本文に加え、ウォーレン・バフェットによる序文、ならびにコラムニストのジェイソン・ツバイクによる注釈と詳細な解説が収録されている。
グレアムが本書やほかの著作において一貫して説いているのは、株価や市場動向の予測ではなく、彼自身が「安全性分析(security analysis)」と呼ぶ、企業の事業実態とバランスシート上の資本構造(capital structure)を丹念に検討し、投資における安全性を確保するための手法である。この点において、しばしば市場や経済環境の先行きを論じる多数の解説書・評論とは、本質的に一線を画している。したがって、彼の著書『Security Analysis』は、その趣旨と原義に照らしても、本来『安全性分析』と訳されるべきものである。「証券分析」という訳語は、誤訳あるいは意図的な超訳である。
一般に、金融市場に対する人々の見方は実に多様である。少し言葉を交わせば明らかとなるが、世界観、すなわち物事の捉え方は人によって驚くほど異なっている(ゆえに、人間関係の平穏を保つには、初対面の相手との会話において、政治や宗教に加え、投資をも話題にしないほうが賢明だと私は考える)。
金融市場という仕組みは、いわゆる複雑系の一種であり、そこに普遍的な法則性を見いだすことは極めて困難である。ここは、因果律や要素還元といった近代科学の基礎的な手法すら通用しづらい、極めてランダム性の高い領域である。そして二〇世紀以降に飛躍的に発展した計算機科学やその応用技術も、必ずしも十分な成果をもたらしてはいない。
ゆえに、この世界を網羅的・体系的に理解しようとする試みは、ほとんど例外なく挫折に終わっている。こうした混沌のなかにおいて、拠り所となり得るのは「うまくやっていくための知恵」、すなわちヒューリスティクスのみである。畢竟、人はそれぞれに独自の信念体系を築き上げることになるが、それが真に妥当かどうかは、実は本人を含めだれにも確かめようがない。
ただ一つ言えることがあるとすれば、それらの信念に一定の客観性・妥当性・再現性が伴っているならば、それを基盤として金融活動を行う者は、結果として経済的に豊かになり得るということである。バフェットが本書の付録で述べているとおり、金融市場において卓越した実績を上げた投資家の多くがグレアムの薫陶を受けた者たちであるという事実は、「安全性分析」が極めて実効性の高い手法であることの証左にほかならない。
一方で、効率的市場仮説の信奉者たちは、バフェットらが長年にわたり市場平均を凌駕し続けている現実を単なる偶然と片づけ、それが必然であった可能性を容易には認めようとしない。私見では、彼らの誤謬はこの特異な現象を「能力の問題」として捉えた点にある。もしそれが真に人間の先天的能力に帰せられるものであるならば、凡人が及ぶべくもない領域ということになる。しかし実際には、それは生得的な才知ではなく、他者への継承が可能な知識の問題である。グレアムの門下生たちが際立った成果を上げたのは、「安全性分析」が凡庸な人間でも習得し得る平明な構造を備えつつ、金融市場の本質を的確に捉えた知的枠組みだったからにほかならない。
この「安全性分析」の概念が世に出てから、すでにおよそ一世紀が経過しようとしている。その間、多くの学者や実務家がより高度で洗練された理論や数理モデルを用いて市場の解明に挑んできたが、その大半は実を結ぶことなく、空理空論が積み重ねられる結果となった。
にもかかわらず、人々がなおも果てなき試行錯誤を繰り返すのは、おそらく「安全性分析」があまりに平易であるがゆえに、かえってありがたみが感じられないからであろう。そして、「どこかに絶対的な真理や正解が存在し、それさえ手にすればすべてが得られる」という幻想は、メーテルリンク伯爵の書く物語が象徴するように、人間の本源的な願望にほかならない。
しかし実務家にとって真に価値あるものとは、理論が整っているかどうかでも、道具の外観が洗練されているかどうかでもない。それが現実の場面で確実に役立つかどうか、である。心眼をもって探さずとも、青い鳥はすでにあなたの足元にいるのである。
本書刊行にあたり、精緻かつ誠実な訳業を担ってくださった井田京子氏、また丹念な編集・校正を施してくださった阿部達郎氏に、心より深謝申し上げる。加えて、本書を世に送り出してくださったパンローリング株式会社の後藤康徳社長に、謹んで御礼を申し上げる。
二〇二五年七月
長岡半太郎
ウォーレン・バフェット
グレアム・ドッド村出身の投資家たちに共通する知的テーマは、ある企業の価値と、その企業の小さな一部分に付けられた市場価格との不一致を探すことです。彼らは、本質的にその格差を利用して利益を得ており、効率的市場仮説(EMH)理論の支持者たちのように買うのが月曜日か木曜日か、あるいは一月か七月かなどとは考えていません。ちなみに、多くの実業家が企業を買収するとき(実は投資家が市場を通じて株を買うのと同じこと)、それが月曜日でも金曜日でも関係ありません。それなのに、学者たちはなぜ企業の一部分である株を買うときには多大な時間と労力をつぎ込んで買いのタイミングの違いを調べようとするのか私には理解ができません。グレアム・ドッド村の投資家たちは、もちろんベータ値やCAPM(資本資産評価モデル)やリターンの共分散などは検討していません。そういったことには関心がないからです。実際、彼らの多くはその意味すら正確には理解していないでしょう。彼らが重視するのは二つの変数、つまり価格と価値だけです。 (続きを読む)